
〇若さゆえの経験不足
〇父親の威光で政界入り
〇みてくれ(ルックス)だけ
――これ、誰に対する批判だと思います?
答えは、合衆国第35代大統領ジョン・F・ケネディ。時に1960年、弱冠43歳で大統領選に挑んだ彼は、世の保守的な人々から様々な批判を受けたんだけど、中でも目立ったのが冒頭の3つ。この時、彼は若さゆえの経験不足を問う声に、こう反論したという。「44歳以下の人間が国家に対して責任ある地位に就けないのであれば、合衆国の建国の父たちは存在し得なかった――」
翻って、小泉進次郎である。
今年、彼は人生で2度目の自民党総裁選に挑んでいる。現在44歳――そして、かつてのJFKと同じく、冒頭3つを始めとする批判に晒されている。中でも風当たりが強いのが、やはり“若さゆえの経験不足”だろう。しかし、JFKの論法に従えば、例えば「維新の三傑」は明治元年の時点で、西郷隆盛40歳、大久保利通38歳、木戸孝允(桂小五郎)35歳である。しかも、彼らはもっと国家運営の経験に乏しかった。進次郎に何の不足があろうか。
日本人は元来、島国特有の保守的な国民性と言われる。いや、自分は違うと反論する人もいるだろう。ならば、別の言い方をしよう――「総論賛成・各論反対」の国民性と。普段は「若い世代にもっと活躍の場を!」と声高に唱えつつ、いざ具体的な話になると「いや、彼(彼女)はまだ早い。もっと経験を」――と口をすぼめるタイプだ。
前置きはこれくらいにして、今回のテーマは、そんな“根が保守的な日本人”の国民性が問われる案件――「小泉進次郎のフェイクニュースを検証する」である。近年、進次郎(※以下、親しみを込めて敢えて敬称を略します)に対するアゲンスト(逆風)がちょっと酷い。特にネットやSNSにおける誹謗中傷が常軌を逸している。中には、人権侵害にあたるものも――。
|
|
|
|
もちろん、政治家だから批判は甘んじて受けるべきだけど――ソレは、真っ当な批判の場合。進次郎のケースは、批判される多くのニュースが曲解されているか、存在しないデマ。また、“進次郎構文”のようにネタ化して、拡散されるうちに、いつしか既成事実化して、更に批判されるという――負のスパイラルに陥るケースも。もはや、これはイジメだろう。大人がこんな状態だから、子どもたちの間でイジメがなくなるワケもなく――。
そこで、当コラムでは、進次郎にまつわる有名なフェイクニュースをいくつか紹介しつつ、客観的な事実を提示して疑いを晴らすと共に、総裁選の最終盤、立候補している5人にはフラットな状態で、正々堂々と戦ってほしいと願うばかりです、ハイ。
えっ、なぜこの話がTVコンシェルジュかって? これは、れっきとした「テレビの見方」に繋がる話なんです。
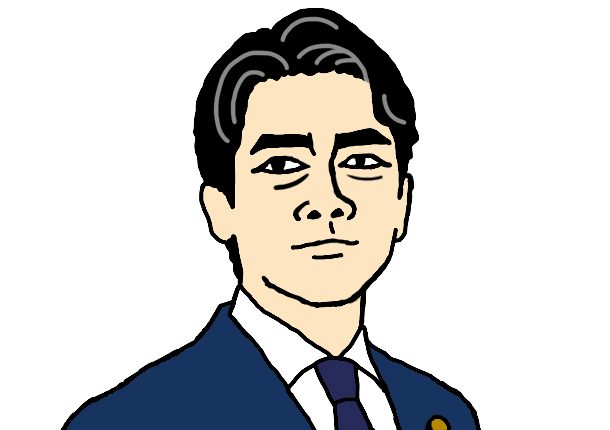
いつ潮目が変わったのか
思えば、進次郎がもっと若かったころ――20代から30代半ばにかけては、今ほど色眼鏡で見られず、ネットやSNSは、むしろ好意的な反応が多かったと思う。潮目が変わったのはいつか。たぶん――2019年9月、彼が38歳で環境大臣として初入閣して、その12日後に出席した、ニューヨークで開催された国連気候行動サミットだろう。そう、あの物議を醸した「セクシー」発言だ。
|
|
|
|
コトの次第はこうである。海外メディアが出席した記者会見で、進次郎は記者たちの質問に時おりユーモアも交えながら、英語で答えた。その中に「気候変動のような大きな問題への取り組みは、本来、楽しいはずであり、かっこいいこと。そしてセクシーじゃないとね(※英語)」という発言もあった。これをロイター通信が「日本の新しい大臣が“気候変動との戦いをセクシーに”と発言」と大きく報じたコトで、日本のメディアがざわついた。
問題は、ロイターは進次郎の発言をポジティブに捉えて報じたのに対し、日本のメディア――例えば、テレビ朝日の『ANNニュース』は、ロイターの記事を取り上げ、「(ロイター通信は)日本政府の地球温暖化への取り組みに懐疑的な見方を示しています」とネガティブなトーンで伝えたのである。他局のニュースも同様に、進次郎の「セクシー」発言に、海外の記者たちが戸惑いを見せたかのような報じ方だった。それを受けて、日本国内のSNSは炎上した。
セクシー発言の真相
だが――真相は違った。あちらの記者たちは戸惑っていないし、ロイター通信の記事を読んだ欧米の人々の間でも炎上していない。なぜなら、あちらでは「セクシー」を「魅力的な」という意味でも用いるから。つまり、進次郎の発言の真意は「気候変動の取り組みを魅力的なものに変えていくことで、若い人たちの積極的な参加を促す」というもの。例えば、スタバにマイタンブラーを持参してプラゴミを減らす行動も、欧米流に言えば「セクシー」になる。そう、進次郎の発言は極めて真っ当だった。
加えて、あの記者会見には、進次郎の隣に、気候変動枠組条約の前事務局長クリスティアナ・フィゲレス氏も同席していた。彼女はかねてより「グリーンセクシー」(環境問題への魅力的な取り組み)が持論で、あのセクシー発言も、進次郎なりに“気候変動問題の大家”に敬意を表したもの。もちろん、ロイターもその意図を見抜き、“今度の日本の若い大臣は、気候変動問題に柔軟で新しいアイデアを持っている”と評価したのである。
実際、いつもは政治家の発言を茶化すデーブ・スペクターさんも、この日の進次郎の発言には「sexyには『とてもわくわくする』意味もあり、米国でも使う」とツイート。また、その後の朝日新聞の取材でも「日本ではまだ意識の低い環境問題をセクシーと表現するのは新しい試み。若者の意識も向けられる」と進次郎の発言を評価した。
|
|
|
|
結局、この問題は、「セクシー」の二次的意味「魅力的な」を知らず、近年の気候変動問題のトレンド(グリーンセクシー)も調べず、ただゴシップ的に進次郎を叩いた日本のメディアの完全な誤報だった。しかし、ソレを受けて炎上したSNSは、以後、進次郎叩きを加速させていく。その意味で、本案件は進次郎に対する世論の風向きを変えた分水嶺となり、極めて罪深い。
レジ袋有料化は誰が決めたか
次は、こちらも進次郎叩きの象徴である「レジ袋有料化」案件である。まず前提として、本案件を起草した人は進次郎ではない。前環境大臣の原田義昭サンである。進次郎が着任する約3ヶ月前の2019年6月3日、原田大臣は環境省内で記者会見して、小売店などで配られるレジ袋について「無償配布してはならないという法令を速やかに制定したい」と述べ、法律を早期に整備する考えを表明した。
その対象は、スーパーやコンビニなどレジ袋を使用する全ての事業者。有料化の時期は、東京オリンピック・パラリンピックを開催する2020年夏(※当時)が目標と。曰く「レジ袋がプラごみに占める割合は多くないが、有料化はプラゴミ削減の象徴になる」――つまり、広報的効果を期待してのものだった。
ぶっちゃけ――本案件は、原田大臣が先に話した通りになった。その後、2019年9月11日に進次郎が環境大臣に就任。前任者の方針を引き継いで、同年12月27日に「容器包装リサイクル法」の省令改正で、レジ袋有料化が正式に決まった。そして翌2020年7月1日から、全国でレジ袋の有料化がスタート。オリンピック・パラリンピックは1年延期されたけど、レジ袋有料化は計画通りに進んだのである。

有料化前に、大勢はマイバッグ派だった
え? それでも実行した環境大臣に責任があるだろうって?――もちろん、それはそう。だが、あの時、進次郎はレジ袋の有料化を止めるべきだったのか。ちなみに、海外に目を向けると、進次郎が大臣に就任した2019年の時点で、欧米各国はほぼレジ袋の有料化か禁止に移行済みだった。そして日本が有料化した翌年には中国、翌翌年にはインドも禁止に踏み切る。そう、国際情勢は有料化が大勢を占め、近年は更に廃止へ踏み込む国が増えている。日本一国だけが、プラゴミ削減のトレンドに逆行するワケにはいかないのである。
もっと言えば、環境省の調査によると、有料化に踏み切る4ヶ月前の2020年3月の時点で、既にスーパーマーケットにおけるレジ袋の辞退率は57%もあった。つまり、マイバッグ持参派が過半数を超えており、有料化することで、むしろ彼らがレジ袋を断る手間が省け、レジの効率が上がったのである。ちなみに、今やスーパーでマイバッグ持参派は9割。レジ袋有料化は、国際的にも家庭的にも、時勢の流れだったのである。
そして、むろん――その主要な目的は、プラゴミ削減の広報的効果。これも原田大臣の発言から今日まで変わりない。
進次郎構文の99%は創作、あるいはキリトリ
さて、ここで進次郎叩きの最も悪質なケース「進次郎構文」を取り上げたい。断言するが、その99%は創作、あるいはキリトリである。もちろん、政治家なので、演説や答弁で分かりやすく伝えようと、コトバが重複することはある。話し言葉を文字起こしすると、まどろっこしい表現になることもある(ソレはみんなそうだ)。だが、巷に出回っている、いわゆる「進次郎構文」は、ほぼほぼデマ(ネタ)と思って間違いない。
なぜなら、その多くがネタサイトからの引用か、伝聞だから。例えば、昨年9月、大竹まことサンがTOKYO MXの『バラいろダンディ』にゲスト出演した際――その時も自民党総裁選の真っただ中だったけど――進次郎について、こうコメントした。「あの人、もしかすると天才かもしれない。『パワーは力だ』って言ったんだぜ。俺はもう腰から崩れ落ちた。もしかすると天才かもしれないよ」。この時は、その場の全員が笑ってオチがついた。でも――どれだけネットを探しても、進次郎がソレを発言したソースが出てこない。となれば、誰かがSNS上で創作したものを、たまたま大竹サンが本人の発言と誤解して、引用したのかもしれない。
ちなみに、「パワーは力だ」は、推測するに、アニメ『新ビックリマン』(テレビ朝日系/1989年)に登場するブラックゼウスの口癖「力こそパワー!」が元ネタだろう。ネタを知ってる世代(30〜40代か)には馴染みの台詞で、今もジョーク的に使われるそう。たぶん、その世代の人が「進次郎構文」として創作したのではないか。
そうそう、進次郎構文のネタ元を見抜く方法に、Googleの画像検索を使う手もある。例えば、以前SNSに、法被を着た進次郎が屋外で氷を扱う写真に「よく冷えた氷だね。」というキャプションが付いた投稿があった。見るからにネタだが、画像検索をかけると、本人のインスタがヒットした。実際のキャプションはこうである。「毎日暑い日が続きますね。写真は週末地元のお祭りで、飲み物を冷やすための準備を手伝った時のもの。少しでも涼しさをお届けできれば…。熱中症にはくれぐれも気をつけてくださいね。」
では、いつ頃から「進次郎構文」なるネタが広まったのだろうか。調べると、どうも戦犯と推察される1つの番組が浮上した。その番組こそ、よく同構文の代表例として挙げられる「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている」の発信元らしい。実際、件のシーンの動画を見ると、いくつか不自然な点もあり、“構文”は作られたものでは……と疑いも湧いてくる。その番組とは――これも先の「セクシー発言」で取り上げた、2019年9月23日の『ANNニュース』(テレビ朝日系)である。
進次郎構文はいかにして作られたか
その動画は、ニューヨークの国連本部で開かれた先のサミットで、進次郎が囲み取材を受けている様子を映している。スーパーは「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている」で終わっており、進次郎もその通りの発言をしている――と思いきや、最後のところで、口が動いてる。よく聴くと、「――思っている“と”…」と言葉が続いている。彼はこの後、何を語ったのか。
調べると、既に同じ疑問を感じた方々が結構いて、SNSやブログなどで指摘している。残念ながら、この『ANNニュース』の完全動画はネット上に残っていないが、NHKはじめ、各メディアがこの囲み取材を記事化しており、一字一句正確な発言は分からないものの(記事化する場合、話し言葉から書き言葉に変換される)、進次郎の発言の意図は概ね分かる。ちなみに、NHKの記事では、前後の文脈も含めて、同シーンの進次郎の発言を次のように記している。「若い世代に対する責任を、私も含めて、みんなが受け止めたと思う。日本は今のままではいけない。今のままでいいなんて、決して思っていない。日本の存在感を発揮することが大事だ」
――おそらく、あの『ANNニュース』は、意図的に進次郎の最後の言葉「と」をスーパーから削り、音声も絞った。発言の続きは、たぶん「――思っている“と”いうことを、もっと言っていかなければならない」。これだと、進次郎が言わんとすることは、“発信力”不足だと分かる。実際、このサミットでも再三、進次郎は日本の国際会議における発信力の低さを指摘し、だから自分が英語で発信する意義を説いている。
いかがだろう。なぜ、『ANNニュース』がそうした意図的な編集をしたのか真意は分からない。しかし、少なくとも、ソレを機に「進次郎構文」なるネタが常態化して、今日まで膨大なデマを生み、1人の政治家の人権(はっきり言ってイジメである)が脅かされている。その想像力は働かないのだろうか。良心は痛まないのだろうか。
なお、この話には後日談があって、その『ANNニュース』は翌年2020年1月3日に「“ポエム大臣”と揶揄も 進次郎氏への期待に異変」と題した特集を組んでいる。その中で、なんと先の「今のままではいけないと思います――」と「セクシー」発言を取り上げ、ネット上に渦巻く批判の声を紹介したのだ。“マッチポンプやん”――そう思ったのは、僕だけだろうか。
メガソーラーは誰が広めたか
最後に、ここへ来て急にトレンド化しているニュースを。そう、“北海道・釧路のメガソーラー”案件である。国立公園の「釧路湿原」周辺の民有地にメガソーラー建設が相次ぎ、国の特別天然記念物のタンチョウなどの生態系が侵される恐れがあるという。そして――なぜか、この案件で進次郎が叩かれている。
そう言えば、釧路湿原のタンチョウと言えば――僕らの世代(50代以上)には、ドラマ『池中玄太80キロ』(日本テレビ系/1980年)で、玄太(西田敏行)がライフワークとして、かの地に度々撮影旅行に出かけていたのを思い出す。ちなみに、同ドラマで長女・絵理を演じた杉田かおるサンが歌った「鳥の詩」の“鳥”が、釧路湿原のタンチョウである。
閑話休題。なぜ、釧路湿原周辺のメガソーラー案件で進次郎が叩かれているのか。発信元の引用を見ると、環境大臣時代に進次郎が日経新聞のインタビューに応じた記事「国立公園で再生エネ発電促進 環境相、規制緩和の方針」に繋がる。そして、ご丁寧にも、進次郎のWikipediaにも最近、同じ批判内容で加筆された跡があり、同問題にかなりスペースを割いている。
うーん…何やら、すごい怨念を感じるけど、そもそもメガソーラー(太陽光発言)を推進したのは、2011年に「固定価格買い取り制度(FIT)」法を成立させた菅直人政権である。ソフトバンクの孫正義サンが旗振り役になったので、覚えている人も多いだろう。だが、その後、メガソーラーが景観を損なうと批判されたり、水害等の原因の疑いをかけられたりと雲行きが怪しくなると、孫サンはさっさとメガソーラー事業を売却。その辺り、機を見るに敏というか変わり身の早さに感心してしまう(褒めてます)。
国立公園の地下に眠る世界第3位の地熱資源
一方、進次郎が環境相時代に推進した国立公園内の再生エネ発電の規制緩和とは、基本、地熱発電である。世界各国は2015年のパリ協定で、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言しており、日本も例外じゃない。ただ、欧州と違って平地が少なく、台風の多い日本は、太陽光や風力発電の伸びしろには限りがある。
そこで、進次郎が目を付けたのが、世界第3位の地熱資源を誇る地熱発電の開発。太陽光や風力と違い、気象に左右されず24時間発電できるので、安定電源になり得る。ただ1つ問題があって、地熱資源の8割は国立公園の地下に眠る。そこで、国立公園内で地熱発電の調査・研究ができるように改正したのが、先の規制緩和である。
ちなみに、進次郎が推進した太陽光パネルは、フィルム型のペロブスカイト太陽電池。“都会の電力は都会で作る”考えのもと、将来的にはビルの屋上や壁面への設置を義務付ける法案も検討したいと語っている。その一方、地方に設置する太陽光パネルについては、環境に配慮し、地域との共生を図ることが重要と、環境アセスメントの対象にした。むしろ規制を強化したのである。
それと、最後に大事なコトを1つ。今回、問題化している釧路湿原の周辺のメガソーラー案件は――そもそも国立公園じゃない。その周辺の民有地である。進次郎を批判するには、ちと無理がある。
――以上、長々と語ってきたけど、何ゆえ、進次郎がここまで狙い撃ちされるのか、正直、よく分からない。仮に、“彼ら”の言うように、進次郎に能力がないのなら、放っておけば勝手に自滅するだろう。政界は、そんなに甘いトコロじゃない。でも――最も身近で彼に接している、決して少なくない国会議員の仲間たちが、そんな進次郎に夢を託している。ソレは事実だ。ソコには、知性とか毛並みとかルックスを超えた、進次郎に何かとてつもない魅力があるのかもしれない。

自民党総裁選の投開票は、10月4日である。
動画/画像が表示されない場合はこちら

