
大企業でも難しかった、国内のEC市場への新規参入
湯浅エムレ秀和氏(以下、湯浅):お菓子つながりで近本さんにおうかがいしたいんですが、どういうふうに最初の一回し、二回しを作っていったのでしょうか。
近本あゆみ氏(以下、近本):ありがとうございます。私も起業の経緯からお話しさせてもらったほうがいいかなと思うんですけど。私はもともと前職がサラリーマンで、リクルートに勤めていました。その時10年ちょっと前ぐらいに、国内向けのECの新規事業の担当をやらせてもらっていたんですが、リクルートという大企業をもってしても、国内市場にECで新規事業として入っていくことって、すごく難しかったんですね。
すでに大きなプレイヤーがたくさんいる中で、売上を作っていく難しさを感じていました。 自分はもともと起業したいなと思っていて、勉強もできたらなという思いでリクルートに入ったので、リクルートにいながら、「自分が起業するんだったら何をしようかな」と考えながら過ごしていました。
ECは国内向けだったらけっこう難しいけど、その当時海外向けにやっているプレイヤーってすごく少なかったですし、成功している会社って、本当に数えるぐらいしかなかったんです。なので「もしかしたら自分にもチャンスがあるんじゃないかな」というのが、最初に思い始めたきっかけです。
日本生まれ日本育ち、留学経験もない中で海外事業に挑戦
近本:本間さんも先ほどお話しされていましたけど、私はめちゃくちゃドメスティックな人間で、日本生まれ日本育ちで、国内の大学を卒業して、留学経験もまったくなかったんです。なので、「どうやって海外事業をやろうかな」と思った時に、まず一緒にやってくれるパートナーを探そうと思いました。
|
|
|
|
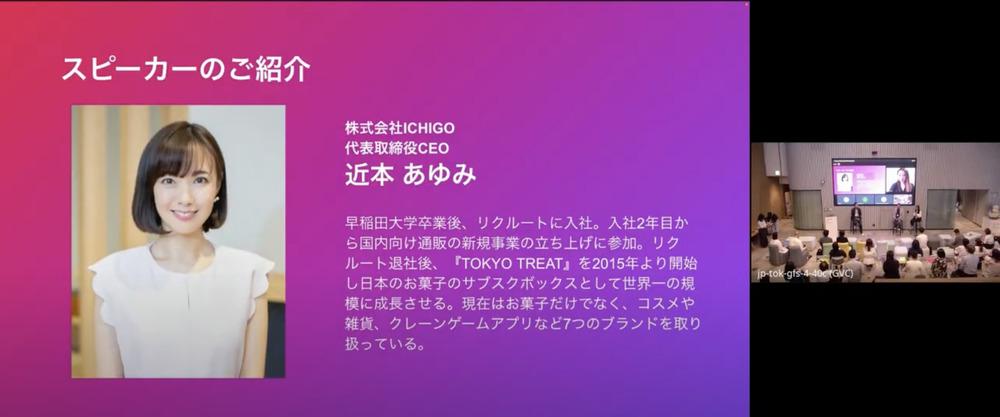
本間さんは恐らくご自身で英語も勉強されてアメリカで戦っていらっしゃると思うんですけど、私の語学力を考えた時に「自分が今から英語を勉強するよりは、できる人と一緒にやったほうが早いな」と思ったんですね。
なので、「一緒にやってくれるパートナーを探そう」と思って、いろいろ探していた時に、台湾やアメリカとかいろんな国に住んだ経験があって、その当時は日本に来ていたインドネシアの人を見つけました。
「こういう海外向けのECをやりたいんですけど、一緒にやりませんか?」と話したところ、「やってみたい」と。けっこう時間はかかったんですけど、最終的には一緒にやってくれることになったので、まず2人で始めました。
なので、「海外向けに日本のものを売りたいです」という構想は私の中にあったんですけど、どんなマーケットで、どんな商品で、どんなターゲットにするかは、けっこう2人で考えたんです。市場調査では、私たちは調査会社とかはぜんぜん使っていなくて、自分たちでやりました。
|
|
|
|
「私はこういうことがしたい」とパートナーに伝えて、パートナーがアメリカでの居住経験があったので、「こういう記事を読んだらいい」とか、「こういうところに情報が集まっている」とか(教えてくれました)。基本的には英語で市場調査をしていろいろ検討した結果、「やはり市場が大きいアメリカに挑戦しようか」という話になりました。
サブスクモデルに目をつけたわけ
近本:「ECでアメリカに何を売ろうか?」となった時に、当時2014年頃は、ちょうどアメリカでサブスクボックスブームがすごく起きていたんですね。
今だとNetflixとかSpotifyとか、情報アクセス型のサブスクのサービスがメインだと思うんですけど、当時はフィジカルな商品を箱に詰めて、アメリカ国内で、サブスクモデルで1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか、定期課金で販売している事業者さんがすごく増えていました。
しかも事業者が多いだけじゃなくて、日本円で言うと年間の売上が1,000億円あるくらいの規模感の会社もちょこちょこあったので、「けっこうこのビジネスモデルはおもしろいな」と思って目をつけました。
サブスクモデルは良いところがすごくいろいろあるんですけど、まず1つは売上を安定して立てやすいんですね。当然定期課金になるので、どんどん売上が積み上がっていきますし、安定して売上を上げることができるのは、1つ大きなメリットです。
|
|
|
|
あともう1つは、日本のものを海外に販売する時に、サブスクだとお客さまに長く付き合ってもらえるんです。なので、一過性の消費では終わらずに、日本の商品を消費することで、日本の文化や習慣を体験してもらう。海外にいながら日本を経験してもらうビジネスモデルとしても、すごくおもしろいなと思いました。
ローンチからすぐに売上が上がった“事業の選定”
近本:市場調査をしながら、「プロダクトはお菓子にしよう」と、最初に日本のお菓子を選んだんですね。Webサイトを作ったり、デザインしたり、写真を撮ったり。あとはWebサイトに載せる英語の文言を書いたりも、全部2人でやりました。その準備期間としてだいたい半年ぐらいかけてローンチをしました。
2015年3月に初めてのサービスをローンチして、ありがたいことに私たちも売上はすぐ上がっていったんです。なんですぐ売上を上げられたかって言うと、やはり山の選定がすごく良かった。サブスク業界がアメリカで徐々に盛り上がってきているというのもわかった上でやっていましたし。
一応、今ブランド展開としては全世界向けにやっているんですけど、メインターゲットをアメリカにしようというのは最初から決めていました。例えばデジタル広告をかけるのも、アメリカをメインに選んでいたのもあって、早く売り上げを上げられました。
私たちがお菓子という商材を選んだ理由も、アリッサさんと近い部分があるんですけども、やはり日本の文化や職人の技を一番感じてもらえるものだということ。あと、ECでやるって決めていたので、軽くて配送しやすいこと。あとは、お菓子は賞味期限が長いものだと1年もったりするので、けっこうECに向いているというのもありました。
あとは、サブスクでやると考えた時に、日本のお菓子メーカーって、ものすごく商品開発を頻繁にやられるので。例えば5年とか10年とかずっと続けてくれるお客さまがいた時に、「飽きさせずに新しいものを提供できるな」という理由もあって、お菓子を選びました。そのあたりが当たって、わりと事業は早く成長できたのかなと思っています。
湯浅:わかりました。ありがとうございます。お二人とも、最初はいろいろ試行錯誤して、リサーチして、自分にないスキルセットを補完してくれる仲間集めをして、しっかり準備して臨んだところと、ローンチしてから比較的順調に伸びていったのは、すごく共通しているなと思いました。
最初は「ぜんぜん受け入れられなかった」HOMMAの事業
湯浅:本間さんは、今まさにアメリカからスタートして、日本+アジアの各国に展開している感じだと思うんですけど、最初の頃はいかがでしたか?
本間毅氏(以下、本間):なんかみんなすごいなと、うまくいっていていいなと思うんですけど。
湯浅:「ローンチしたら、ぴゅっといきました」というのはすごいですよね。
三木:ちょっとカッコつけてるだけです(笑)。
湯浅:(笑)。
本間:いや、みなさんすごいんですけど、僕はぜんぜんすごくなくて。僕、実は起業2回目なんですよ。この前『ザ・スタートアップ ネット起業!あのバカにやらせてみよう』という本が復刊しましたけど、あそこに名前が出てくるぐらいの時代の人なので、古いんですね。学生時代に渋谷で起業していました。
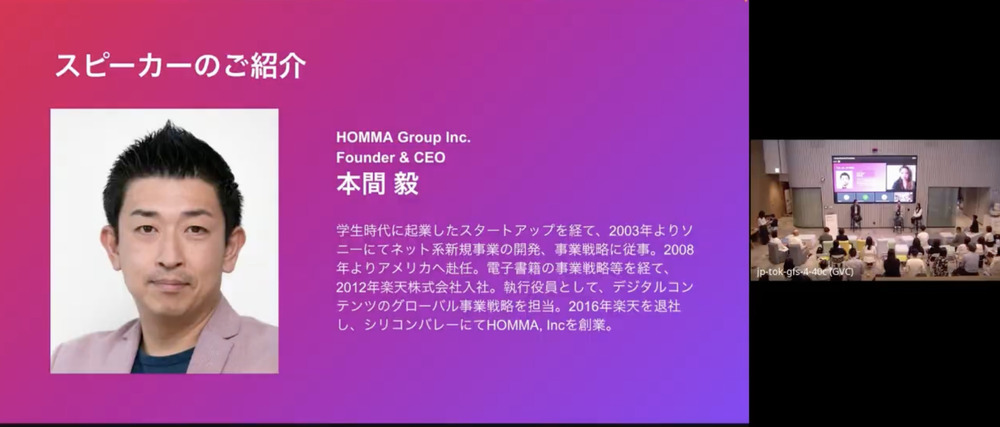
1回目の起業があって、実はそこから脈々といろんな人と知り合いだったので、立ち上げる時の資金調達は比較的まあまあうまくいって、いきなり4.5ミリオンドルぐらい調達してやっていたんですね。
「住宅版のテスラを作りたい」というビジョンがあって、ハードウェアとソフトウェアを垂直統合して、完成されたスマートホームの体験を作ろうとやったんですけど、結局なかなかスケールしないんですよ。
アメリカって、家を建てるのに2〜3年ぐらいかかるので、1つのプロジェクトに最初に2〜3かけていたら、一生あっても時間が足りないなと。なので、テクノロジーを作って、家を建てている他の人に売りに行こうと。まさに今のモデルでやろうとしたんですけど、まったく相手にしてもらえなかった。
やはり一般的に言って、ビルダーさんとか工務店さんは古い業界の人なので、テクノロジーがなくても生きていけるし食っていける。「そんな新しいことをしてリスクを冒してどうするんだ」という話になることが多く、最初はぜんぜん受け入れられなかったんですね。
なので、しょうがないからもう1回立ち返って、自分たちで家も建ててビルダー、デベロッパーになるしかないと。「毒を食らわば皿まで」じゃないですけど、ハードウェアも自分たちでやることになって、やはり元の道に戻ったんですよ。ここまででもう1年半ぐらい経っているので(笑)、なかなかすぐにはうまくいかなかったんです。
「住宅版のテスラを作りたい」というビジョンにこだわり成功へ
本間:でも、そこから歯を食いしばって、もう1回お金を集めて、自分たちで理想的な住宅を作ろうとしました。デザインも超カッコいいし、テクノロジーも全部ビルトインされているし、いろんな工夫が詰め込まれたすばらしい住宅がやっと1軒できたんですけど、ここまででもう4年ぐらい経っています。
でも、そこからがうまくいっていて、1軒建てたら「これをもっと大きくしよう」ということになりました。自分たちがデベロッパーをやると決めたので、もうちょっとお金を集めて、18世帯の賃貸住宅を自分たちのプロジェクトで建てました。自分たちでお金を作って、地面を買って、設計してというのをやったんですね。
今から3年ぐらい前にこれが立ち上がったんですが、やってみたら、賃貸住宅としては周辺の住宅相場よりも10パーセント以上家賃が高く取れて、現在もフル稼働しています。かつ、1年更新なんですけど、賃貸の更新率が全米平均より20パーセント高いんですよ。
「これはすごい」ということになって、ようやくテクノロジーのトラックレコードや実績を持って、外部のデベロッパーさんにライセンスを売ることができました。ここまで約8年かけてやっています。
なので、プロダクトマーケットフィット(PMF:商品やサービスが市場に適切に受け入れられている状態)に行くまでが、ものすごく長かった。これは不動産開発とか家作りのネイチャーがそうだからということと、あとはやはり他の人がやらない理由が、自分でやってよくわかったなという感じです。
スマートロックを1個だけ作って売りにいけば、もうちょっと早くできたかもしれないですけど。そうじゃなくて、やはりテスラのように、いろんな優れたデザインのハードウェアと優れたユーザーエクスペリエンスを作るためのテクノロジーを、ちゃんと中に埋め込んで作ることにこだわったので。その分、他がついてこれないところまで来たかなって思います。
たぶん、みなさんとはぜんぜん違って、この間にチームは3回転ぐらいしています。お金も3回ぐらい集めていますし、ハードコアと言えばハードコアなんですけど、そんな経緯でここまで来ました。だから、最初の一回しがやっと最近回りましたみたいな答えになると思います。
うまくいかない中で8年事業を続けられた理由
湯浅:なるほど。今日はスタートアップの方も多いと思うんですけど、まさにおっしゃったプロダクトマーケットフィット。プロダクトがマーケットのニーズを満たして、お客さんがどんどん「欲しいです」と言ってくれる状態まで持っていくのが、最初はすごく大変ということですね。
先ほど「8年かかった」とおっしゃいましたが、なかなか8年間やり続けられる人っていないと思うんですけど、その原動力はどこにあったんでしょうか。
本間:僕が最初に20代で会社を作った時は、「金持ちになりたい」「有名になりたい」「なんか成し遂げたい」みたいな感じだったんです。
湯浅:ギラギラした感じですね。
本間:ワナビー・スタートアップ経営者で、お金以外は半分くらい達成したかなと思っているんですけど。とはいえ、その時の人たちがやはりお金を出してくれて、もう1回会社を作ることができました。
僕はソニーと楽天で13年間サラリーマンをやっていたんですけど、その間にアメリカに行って住んでみて、やはり住宅が古いと。日本はこれだけすばらしい住宅技術があるのに、アメリカはユニットバスやシステムキッチンがないんですよ。だけど、アメリカにはそれがないのに、家はどんどん必要になっているし、これはすごいオポチュニティだと。でも誰もやっていないので、そこをやりたいと思いました。
どんな困難も乗り越えられた「原動力」
本間:やはり自分がアメリカで感じた不便な生活を、より便利にしていく。人って一生のうち40パーセントぐらいの時間を家の中で過ごすので、ここが未来的になったら、もしかしたら車やスマホよりもインパクトが大きいかもしれないという思いで、未来を作る仕事がしたいと思ってやったのが、ずっと原動力(になっています)。
どんなに投資家に断られようとも、いろんなことが起きようとも、これを続けていられるのは、自分のためにやっているというよりは、社会のためにやっているという思いがあるから。人の未来を作っていると思えるから、今がんばれている気がすごくします。
なので、お金は後からついてくるというか、スタートアップってキラキラしているように見えると思うんですけど、実はその10倍というか100倍ぐらい、水面下ですごくいろいろなことをやっているので、やはりモチベーションってすごく大事だなと思います。
時々アリッサさんとも話をするんですけど、お互い起業家で悩みを持っているので、そういう悩みながらも、やはりミッションの実現というか未来の実現のために向けてがんばっている感じだと思います。
湯浅:なるほど、さすがですね。ありがとうございます。

