
クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、料理研究家のウー・ウェンさんがゲストの後編です。
母親の家庭料理がベースになっている
小竹:ウー先生のお母様もお料理上手だそうですが、記憶に残っているお料理はありますか?
ウーさん(以下、敬称略):どんなものもおいしく作ってくれたので、やさしい味しか記憶には残っていないかもしれない。うちの子どもたちは、おばあちゃんのいんげん炒めや豚の角煮をすごくおいしいと言っていますね。
小竹:どこが違うのでしょうか?
ウー:たぶん素材だと思う。豚の角煮は中国は絶対に皮つきだから滑らかさが全然違うし、お醤油もたまり醤油に近い加熱用のお醤油なんです。日本では味わえないような味だからこそ好きなのかもしれないです。野菜も大陸なので味が濃くて、いんげんもすごく豆の味がします。
|
|
|
|
小竹:日本は生食で食べられる瑞々しいものが多いですが、中国はやはり加熱がベースになっている感じですか?
ウー:そうですね。だから、炒めてもそんなに水が出ないので、それはきっと水と土の関係があるのではないかと思います。
小竹:あと、素材を上位に置いたときに、どう活かすかという部分もありますよね。
ウー:私が生まれ育った時代は決して豊かではなかったので、母親はやさしい味を活かした、素材のおいしさを活かした料理ばかりでしたね。それこそうちの母親も凡人ですから(笑)。凡人が作る料理が一番的確ではないかなと思います。
小竹:お母様から教えてもらったものが、今の先生のお料理のベースにもなっていますか?
|
|
|
|
ウー:それしかないです。ただ、教えてもらったことは一度もないし、作ったこともなかったんです。日本に来て結婚して、作らなければならないという現実になったときに、どう作ればいいのか悩んで…。お母さんの味や、こうやって作っていたかなと思い出したものしかなかったので、ベースは母の家庭料理です。
“毎日の食事作り”で大切な5つのこと
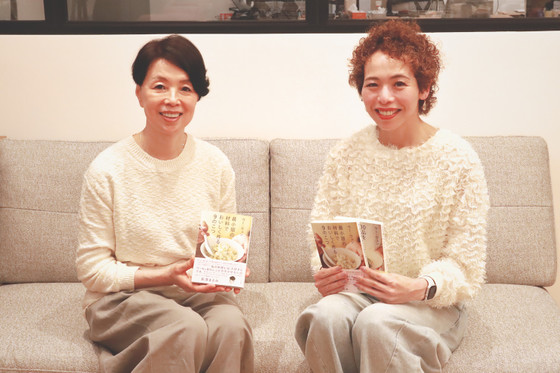
小竹:先月発売された新刊『最小限の材料でおいしく作る9のこつ』について伺いたいのですが、「毎日の食事作りの中で5つの意識改革」というお話をされていますね。
ウー:私はとっくに還暦を迎えてもう孫もいるのですが、30〜40代のときにはここまで言い切ることはできなかった。結婚や子育てなども含めて、いろいろと経験してきたからこそ、これがいるとかこれがいらないといったことがはっきりとわかってきたんです。
小竹:うんうん。
|
|
|
|
ウー:私は凡人なのでたくさん失敗もしたので、次の方たちが失敗しなくていいように、「このくらいになれれば十分だよ」と言えたことが今はとてもうれしいです。
小竹:その5つの意識改革を紹介したいのですが、1つ目が「料理名から考えない」。
ウー:そもそも素材を言わないとわからない料理名が多いじゃないですか(笑)。トマトと卵を炒めるなら「トマトと卵の炒めもの」にしてほしいですよね。
小竹:「トマトと卵の炒めもの」でトマトと卵を買いに行くというよりは、先生はあるもので料理を考えることが多いですよね?
ウー:そうそう。家庭料理ですので、冷蔵庫にあるものを消費しないといもったいないじゃないですか。
小竹:2つ目が「塩と油だけでいいと心得る」。
ウー:人間が生きていく上で必要な基本的要素はなんでしょうか。水分、油分、塩分があれば生きていけるんです。どんどん人類が進化して技術が発達したから醤油やお酢などが作られましたが、最初は塩と水だけだったはずです。だから、これさえあれば生きていけると思っていてください。
小竹:本には「味付けは忘れてしまってもいいくらい」とも書いてあります。
ウー:だって、素材がどんどんおいしくなっていませんか。日本に来たばかりのときの食材と今の食材では味が全然違います。
小竹:野菜とかもそうですよね。
ウー:昔はトマトは酸っぱかったです。「トマトと卵の炒めもの」を昔からよく作りますが、多少はお砂糖を入れないとおいしくなかった。今は砂糖を入れたら、おかずなのかデザートなのかフルーツなのかよくわからなくなってしまうので、塩で中和したほうがいいですね。
小竹:じゃあ先生のレシピもアップデートされているのですね。
ウー:そう。私もアップデートされています。毎日作るとそうなっていく。だから、毎日作っていればみんなそうなりますよ。
自分の“感覚”で料理を作ることも大切
小竹:3つ目は「季節のものを食べる」。
ウー:「中国の食生活は医食同源だね」とよく言われますが、私たちが中国にいるときに「旬」とか「医食同源」といった言葉は、会話の中では絶対に出てこないです。
小竹:意識をしなくても自然にそうなっていくということ?
ウー:そうなんです。「私は今日、医食同源だよ」なんて言ったら頭がおかしくなったかと思われてしまいます(笑)。日本に来てから「医食同源」という言葉を聞くようになりましたね。でも、日本だってそもそも医食同源ですよ。
小竹:どういったところがですか?
ウー:世界はどこの国も医食同源だと思います。その国、その地域の食材で人間は育っているので、絶対にそれしかないと思いますね。
小竹:やっぱり季節のものを食べたりすると体の調子いいがですからね。
ウー:体が求めているし、人類は自然と共に生きているのだから、与えられたものを素直にいただくのが、トラブルがなしで生きていく一番の方法です。
小竹:4つ目が「完璧をやめましょう」。
ウー:私たち凡人には無理ですよ(笑)。それは忘れないでくださいね。
小竹:レシピ通りに作ることが正義みたいな感じがありますが、自分の感覚で作ることも大切ですよね。
ウー:そうです。だって、今日のトマトと明日のトマトは絶対に同じではない。一期一会です。毎日作ることによって、今日は水分が多いとかがわかるようになって、それに対しての火や調味の加減も自然と覚えていくんです。

沖縄の新鮮な皮付き豚で作った紅焼肉(豚の角煮)
小竹:そうですよね。
ウー:そうです。だって、今日のトマトと明日のトマトは絶対に同じではない。一期一会です。毎日作ることによって、今日は水分が多いとかがわかるようになって、それに対しての火や調味の加減も自然と覚えていくんです。
小竹:私はよく料理を失敗してしまうのですが、そういうのも受け入れていいということですね。
ウー:いいと思いますよ。明日また食べるんですから。
小竹:5つ目は「中火以下で作る」。
ウー:中火であれば、自分も追われることがないし、素材にもストレスをかけすぎないで済みます。
小竹:強火だと焦げますけど、弱火で焦げて失敗することはあまりないですもんね。
ウー:加熱というのは温めることです。強火にしても中火にしても水分が100℃まではいかないので結果は一緒。それなら凡人は弱くしたほうがいいかも(笑)。
小竹:この5つのポイントは、先生が長年いろいろと経験されて培われたものなのですよね?
ウー:そうです。今の私が言えることです。いろいろな経験をして素材を大事にするようになり、味にやさしさも一緒に出てきたかなと思います。
小竹:シンプルな料理を何度か作ることも大事だと先生は言っていますよね。
ウー:練習ですよ。スポーツマンだって練習で成果を出すじゃないですか。何事も練習が重要だと思います。
小竹:家庭料理を練習するという考えはなかなか浮かばないかもしれません。
ウー:毎日食べなくてはいけないので、毎日練習をしなければいけない。それをちょっと意識することによって、あっという間に上手になりますよ。
小竹:くり返し作ることで、前よりおいしくなったみたいな気づきもありますよね。
ウー:前回はここをちょっと失敗したかもというところから、二度は失敗しないようにすることで上達につながります。
“できない自分”は認めなくていい
小竹:ウー先生にとって「食べる」とはどういうことですか?
ウー:普通に聞こえると思いますが、「生きること」ですね。それがないと生きていけない。生きていくのであれば楽しく食べるのが一番じゃないですか。
小竹:そして、料理も楽しいですしね。
ウー:そうなんです。どうせ食べるのであれば楽しくやりたいし、食べなければならないから、楽しくやったほうが自分にもプラスになると思います。
小竹:料理を作る、食べる、作ってもらう。先生はどれがお好きですか?
ウー:誰だって作ってもらったほうがいいでしょう(笑)。
小竹:料理家の方は作るという意見も多いのですが…(笑)。
ウー:私は食べたいです(笑)。自分は何もしないで、料理を出してもらうのが一番の理想ですよ。
小竹:普段作っているだけに、おいしい料理が出てくるとすごく感動しますよね。
ウー:ただ、「食べる」と「作る」は2つのことを考えないといけないです。理想は何もしないでおいしいものを食べたい。でも、現実は毎日作って食べて健康を維持していく。それなら苦にならないで楽しく作っていくことが大事ですよね。
小竹:完璧を求めすぎないことも重要ですよね。
ウー:完璧を求めると、できない自分が嫌になるじゃないですか。だから、できない自分を認めなくていいです。明日はできるようになればいいんだから。
小竹:ウー先生が今後やってみたいことは?
ウー:孫が生まれたのですが、これからたくさん食べるじゃないですか。だから、もっともっと食材を大事にして、おいしい料理をたくさん作って、孫ワイロを送りたい(笑)。
小竹:今でもいけそうですけど、さらにですか(笑)?
ウー:子どもたちにおいしさを感じさせることで、本当に人生が変わってくると思います。だから、高価なものではなく、日々の素材を知らせること。そうすれば好き嫌いがなくなるし、好き嫌いがなくなることはとても幸せなことです。
小竹:健康でもいられますしね。
ウー:そうです。ピーマンが嫌いだからといって、細かく刻んで隠して食べさせたりするより、ピーマンをおいしく作って、これがピーマンなんだよと教えることも知育だと思います。
小竹:ピーマンの苦味もおいしいということを伝えるのも必要ですよね。
ウー:知らせることはすごく大事です。たまたま我が家には新人がいるので、この新人に対して、今まで自分の子どもを子育てしていたときの失敗がなるべくないようにするのが私の目標ですね。
小竹:私も子育て真っ最中なのですが、先生のお話を聞いていろいろな悩みが解消されて楽になりました。
ウー:悩んでも解決の方法はないです。だから解決しないほうがいいです。明日うまくやればいいってことですね。
(TEXT:山田周平)
ご視聴はこちらから

🎵Spotify
https://hubs.li/Q02qmsmm0
🎵Amazon Music
https://hubs.li/Q02qmslg0
🎵Apple Podcast
http://hubs.li/Q02qmztw0
【ゲスト】
第30回・第31回(5月2日・16日配信) ウー・ウェンさん

中国・北京で生まれ育つ。ウー・ウェンクッキングサロン主宰。1990年に来日。友人、知人にふるまった中国家庭料理が評判となり、 1997年にクッキングサロンを開設。医食同源に根ざした料理とともに中国の暮らしや文化を伝えている。近著に『最小限の材料でおいしく作る9のこつ』(大和書房)。他著書に『本当に大事なことはほんの少し』『10品を繰り返し作りましょう』(ともに大和書房)、『ウー・ウェンの麺ごはん』『ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理』(ともに高橋書店)、『ウー・ウェンの毎日黒酢』(講談社)など多数。
プロフィール写真:福尾美雪
料理写真:広瀬貴子
HP: ウー・ウェン クッキングサロン
Instagram: @wuwen_cookingsalon
【パーソナリティ】
クックパッド株式会社 小竹 貴子

クックパッド社員/初代編集長/料理愛好家。 趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』(日経BP社)など。
X: @takakodeli
Instagram: @takakodeli

